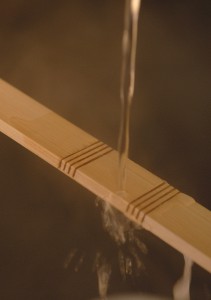博多曲物のできるまで
◯ 側板製作
-
1用いる杉材。
最低1年以上乾燥させて使う。
-
2側板の切り口を整える。
-
3側板の荒削り。
木の目を読み、0.5mmずつ
削る作業を繰り返す。
-
4湯槽に湯を沸かす。
-
5つくるものに応じて側板の
幅を決め、断裁する。
-
6同様に、側板の長さを決めて
断裁する。
-
7表面を0.1mmずつ削る作業
を繰り返し、つくるものに
応じた薄さに仕上げる。
-
8厚みをチェックする。
-
9板の端の重ね合わせる
部分に鉋をかけて削り、
滑らかにする。
-
10 煮立った湯に側板を
漬け、アクを抜きながら
10~30分ほど煮る。
-
11柔らかくなった側板を
引き上げる。
-
12巻木に素早く巻きつけ、
反対からも巻きつけて
曲げる。
-
13板の端を重ね合わせる。
-
14合わせ目を木挟ではさみ、
かたちを整える。
-
15日陰で4〜5日間
乾燥させる。
-
16重なる部分に糊を塗り、
乾いたら縫錐で孔をあけ、
桜の皮で綴じる。
-
17綴じ終わったら、
底板をはめる。
仕上げに磨きをかけ、
水を入れるものは塗装し、
絵付けするものには
絵を描く。
◯ ポッポーお膳の枠製作
-
1ポッポーお膳(檜材を使う)や
三方などの角物は側板を煮ず
曲げる箇所に紐幅の切り込み
を入れる。
-
2切り込みを入れた部分に
熱湯をかける。
杉材を使う場合はアクが
強いので、全体に湯をかける。
-
3手早く曲げる。
-
4合わせ目を木挟ではさむ。
-
5乾燥させ、桜皮で綴じ、
底板をはめ、
絵付けして仕上げる。
曲物づくりの道具
・手と目を信じ、手間を惜しまず
曲物は古くから日本中で広くつくられてきた。それは、つくりやすかったからでもある。木目の美しい木を伐り、それを割って薄い板をつくり、曲げ、樹皮でつなぎ合わせるだけ。塗装もしない曲物は、姿かたち同様、工程もごく単純だった。使う道具も、古くは鉈、鏟(細長い片刃の両端に木製の柄がついていて、それを両手で持ち、手前に引いて材の表面を削る)、縫錐(目通し)の3つが基本だった。 室町時代に入ると小さな細工ができる横挽き鋸が普及し、近世の初めには薄板の表面を整える台鉋が一般化した。また、大鋸や手斧、槍鉋なども使われた。 現在は、それらの作業をグラインダーやカッターなどの機械がこなすため、曲物づくりの道具は意外なほど少ないが、それらの道具のほとんどは、職人自身がつくる。また、そこには絶えず、日々の作業から得たアイデアや工夫が盛り込まれる。 例えば、曲物づくりの要ともいえる側板の曲げ作業で使う巻木には、不要になった消防ホースの生地が使われている。先代までは綿布を使っていたが、適度に水分を吸収し、板を冷やさないで巻けることに気づいて変えたのだという。その巻木の木地は、いつから使われているかわからないほど古い。そんな道具が工房のあちこちで現役なのも、18代続く家業ならではのことだろう。
- 弁当箱の底板の型。
-
曲げた側板を仮止めする木挟と止め具。
先々代のころから使っているものもある。
-
柔らかくした側板を曲げるための「巻木」。
大小の木地に消防ホースの生地をつけたもの。
- 小振りの曲物づくりに活躍する木製ピンチ。

(左から順に) 小刀:桜の皮を切るなど、手作業の必需品。 縫錐:やすりをグラインダーで削り、樫の柄をつけて自作した。目通しともいう。 愛用の博多鋏:10年以上使っているが切れ味は変わらない。 縫錐:使うものによって幅が微妙に違う。これも自作したもの。
-
側板を煮る湯槽と押さえ具。
煮る時間は厚さによって加減する。
溶け出たアクが戻らないように
板を動かし続ける作業は、
見た目より力を要する。
-
合わせ目を綴じるための桜の皮。
秋田から取り寄せた桜の樹皮を
1~2ヶ月ほど水に浸け、
水分を含んで柔らかくなった鬼皮の両面を、
なめらかになるまで繰り返し削いでいく。
つくるものに合わせて細かく切って使う。
-
曲物用の物差し。
「七寸飯櫃 胴高サ五寸二分
蓋帯一寸一分 厚ミ一分三厘 3.9m/m」
など、つくるものごとに寸法が
細かく記されている。
寸や分が現役の世界だが、
いまはmmやcmも使う。